
SERVICES
サービス内容
慶事、仏事などこんなときにご利用ください
シーンにあったのし・メッセージカードをご用意致します。

ご婚礼内祝

結婚式を催す場合は、そこにお招きして引出物を贈ることが内祝になります。ただし、ご祝儀が高額でその引出物では不十分だと感じた場合や結婚式は行なわない、結婚式にお招きできなかったけれどお祝いをいただいた場合には、婚礼内祝としてお礼の品を贈ります。
のし紙は二度とあってはならないことから、「結び切り」ののし紙を選び、表書きは「内祝」や「婚礼内祝」または「寿」とします。下には二人の名前を書いても良いのですが、本来その家の祝事と考えるため○○家に頂いたお祝いは、○○家の姓で贈ります。新郎は新郎の姓で、新婦は新婦の姓で贈ると良いでしょう。
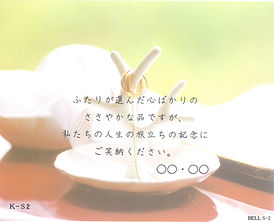


ご婚礼引出物
引出物は、結婚式に出席してくれたゲストへの“感謝のしるし”として、料理と同じくらい大切なおもてなしのひとつです。
カタログギフトや食器、タオルなどの“引出物”に、バームクーヘンや紅白饅頭などの“引菓子”のほか、鰹節や昆布などの“縁起物”を組み合わせて贈るのが一般的です。
ゲストからいただくお祝い(ご祝儀)のお礼として、両家から渡す記念品ですので、本当にいいものを選びましょう。



ご出産内祝

出産内祝には、「子宝に恵まれた幸せのお福分け」という意味が含まれ、赤ちゃんの初めてのご挨拶になります。また赤ちゃんの誕生の報告と、赤ちゃんの名前のお披露目にもなりますから、「これからよろしくお願いします」という気持ちを込めて、贈り物を選びましょう。
出産祝いをいただいた方には、「お宮参り」が済んだ頃にお返しの品を贈ります。
出産は何度あってもおめでたい出来事なので、出産内祝には何度でも繰り返し結べる「蝶結び」ののし紙を選ぶのが一般的ですが、ベルでは赤ちゃんのお披露目にふさわしい、可愛らしいのし紙や包装紙、赤ちゃんのお写真を入れた命名札、メッセージカードをご用意できます。また、赤ちゃんのお名前の入った「名入れギフト」も数多くございますので、ご満足いただける贈り物がベルでみつかることと思います。
津嶋神社祈祷命名札
日本全国で当社だけの取扱いです。

健康と無事を願う
祈祷を授かった命名札です

津嶋神社とは
子供の守り神として
全国的に名高い
神社です
毎年大祭は8月4日~5日(2日間)当日はJR予讃線の詫間駅~海岸寺駅間にJR臨時駅「津嶋の宮駅」が1年に2日だけ開業します
沖合にある孤島の本殿に参拝できるようこの2日間だけ橋が渡され子供の健康な成長と無事を願う大勢の参拝客で賑わう全国的にも珍しい神殿です ぜひお参り下さい













快気祝

病気やケガが治ったら、お見舞いに来ていただいた方やお世話になった方に回復の報告をかねて、お礼の品を贈ります。
「(病気やケガが)後に残らないように」という意味をこめて、食べたり使ったりするとなくなる「消え物」と呼ばれる品物を贈るのが快気祝の基本です。
食べ物であれば、お菓子・コーヒー・お茶・調味料などが一般的。また、「(病気やケガを)洗い流す」という意味で、洗剤や入浴剤、石けんなども快気祝いとして選ばれることが多い品です。
のし紙は(病気やケガを)二度と繰り返さないことを願い「結び切り」ののし紙を選び、表書きは、全快の場合は「快気祝」、まだ通院や自宅療養、リハビリがあり全快とまではいかない場合は、一区切りつける意味で「内祝」や「御見舞御礼」にすると良いでしょう。
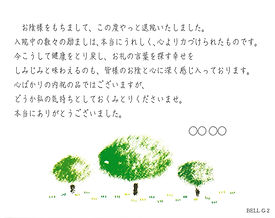


ご新築内祝

新居が完成したらお世話になった方や友人を招いて、新居のお披露目をします。
一般的には、新築披露の祝宴で引出物を贈る事で、お返しに代えます。
新築内祝に贈るものとして、建物(入れる物、器)が完成したことに由来して、グラスやカップなど「入れる物」や、「家を焼かない(やかん)」としてやかんなどを選ぶ方もいます。
のし紙は「蝶結び」ののし紙を選び、「新築内祝」か「内祝」と表書きをして贈ります。
なお、マンションや中古住宅を購入した場合は、表書きを「内祝」とすると良いでしょう。



お香典返し

仏教では四十九日までは死者の霊が家にいるとされ、四十九日の法要で死者に審判が下され運命が決まるとされています。魂が無事に成仏されることを願い、この四十九日までを忌中といい、他に不幸が及ぶことを避け、忌明けしてから初めて香典返しを配ります。
人生、喜びと悲しみは表裏一体といいますが、冠婚葬祭という人生最大の四つの儀式のうちで、結婚が吉事の重要な儀式なら葬儀は凶事の最も重要な儀式です。
お香典返しは、本来、持参してお礼をのべるべきものですが、現在では挨拶状を添えて配送するのが一般的な方法となっています。
ご挨拶状は仏式や神式など宗派により数十種類あります。またタイプも色々とご用意致してございますので、お客様に合ったものをお選びください。
仏式の法名・戒名・神式の命名は誤りがないよう楷書で正確に写しとりくださいませ。
最近��の傾向として読みやすい 二つ折のカード型挨拶状を選ぶ方が多くなってきています。
法事の引出物
故人を供養する法事の際、参列者から仏前に頂いたお供えのお礼として、感謝の意味を込めてお返しするお品物を法事の引出物・法事のお返しなどといいます。法事の引出物は、慶びごとではないためお茶やコーヒー、海苔などの「形に残らない物」「消え物」が一般的で、軽くてかさばらず、持って帰りやすいものを選ぶと良いでしょう。




その他の内祝・記念品・プレゼント
初節句内祝・入学内祝・開店内祝・コンペ賞品・記念品・お中元・お歳暮・各種お祝いなど様々な贈り物に対応致します。
引っ越しのご挨拶や退職時のお礼などのプチギフトにも最適な1000円以下の商品も多数ございます。
ラッピングやシーンに合わせたメッセージカードも承ります。



豊富な商品やサービスの中から先様が欲しいものを自由に選べるカタログギフトは出産祝いや結婚祝い、内祝・香典返しなど、さまざまなシーンで多くの方に贈り物として選ばれています。
ベルでは、業界No.1の品揃えと商品の品質の高さの「リンベル」、一流メーカー商品から、生活必需品まで幅広く掲載し、体験型の商品が多いのが特徴の「ハーモニック」、さまざまなテーマを設けながら商品を紹介しており「選ぶ楽しみ」を感じていただける「マイハート」の他、グ�ルメや香川県産品、和牛に特化したものなど様々なカタログギフトを取り揃えております。
カタログギフト


